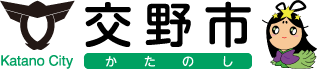公開日 2021年04月26日
更新日 2025年11月28日
自己負担の限度額は所得区分に応じて下表のとおり決められています。
医療機関等で1か月(同一月)に支払った保険適用の医療の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により超えた額を高額療養費として、後日払い戻します。
※同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。
※入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含まれません。
| 負担割合 |
限度区分(所得区分)※資格確認書にはローマ字で表記されます |
判定基準 |
自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位) |
| 3割 |
現役並み所得3 (現役3) |
同一世帯に住民税課税所得額が690万円以上の被保険者がいる場合 |
252,600円+1%(注1) (140,100円(注5)) |
|
|
現役並み所得2 (現役2) |
同一世帯に住民税課税所得額が380万円以上の被保険者がいる場合 |
167,400円+1%(注2) (93,000円(注5)) |
||
|
現役並み所得1 (現役1) |
同一世帯に住民税課税所得額が145万円以上の被保険者がいる場合 |
80,100円+1%(注3) (44,400円(注5)) |
||
| 2割 |
一般 (一般2) |
3割負担に該当せず、住民税課税所得が28万円以上の被保険者が同一世帯にいる場合かつ、以下のいずれかに該当する場合 ・同一世帯に被保険者が1人の場合 公的年金等の収入+その他の合計所得金額が200万円以上の場合 ・同一世帯に被保険者が複数人いる場合 公的年金等の収入+その他の合計所得金額が320万円以上の場合 |
18,000円(注4) (年間上限144,000円) |
57,600円 (44,400円(注5)) |
| 1割 |
一般 (一般1) |
住民税課税世帯で、3割及び2割負担に該当しない場合 |
||
|
低所得2 (区2) |
同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1に該当しない場合 | 8,000円 | 24,600円 | |
|
低所得1 (区1) |
以下のいずれかに該当する場合 ・同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個人ごとの所得が0円となる場合(公的年金等控除額は806,700円として計算。給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除して計算。) ・同一世帯の方全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している場合(老齢福祉年金受給者のみが低所得1となります。) |
15,000円 | ||
(注1)「1%」は医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注2)「1%」は医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注3)「1%」は医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注4)2割負担である方について、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます(入院の医療費は対象外)。対象の診療月の自己負担限度額(月額)は、【6,000円+(外来個人の総医療費−30,000円)×0.1】または18,000円のいずれか低い方となります。
※同一の医療機関での受診では、上限以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。医療機関が複数の場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日、高額療養費として払い戻します。
(注5)被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
「現役並み所得2・1」または「低所得2・1」に該当される方
下記のいずれかの方法にて、同一医療機関で同一月の保険適用の医療の自己負担限度額を超えることなく受診することができます。(外来の場合、入院の場合いずれも)
1.マイナ保険証を利用して医療機関等を受診(マイナ保険証とは、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのことです)
2.自己負担限度区分が併記された資格確認書を医療機関等に提示
※令和7年8月1日以降は、これまでの「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」に代わり、自己負担限度額が併記された「資格確認書」をご提示ください。
※自己負担限度区分が併記されていない方は、申請をしていただくことで、区分が併記された資格確認書の発行を受けることができます。
高額療養費支給申請について
自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、高額療養費の支給対象で手続きが必要な方には、大阪府後期高齢者医療広域連合より案内通知とともに支給申請書が届きます。申請書は当課窓口へ郵送または持参にてご提出ください。なお、一度申請されると、口座番号等を変更しない限り、再度申請する必要はありません。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合から送付)
- 本人確認書類(例:マイナンバーカード・対象者の後期高齢者医療資格確認書など)
- 振込口座のわかるもの (預金通帳など)
- 対象者のマイナンバーを確認できるもの