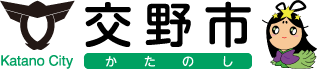公開日 2021年09月02日
更新日 2023年03月24日
令和5年3月13日に、「交野節」が大阪府の記録作成の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択されました。
枚方市で活動する美谷川会、交野ヶ原交野節・おどり保存会とともに、交野市私市で活動する私市・音頭保存会が保持団体となっています。
詳細は、下記リンクの大阪府報道発表資料をご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=47048
交野節とは
交野節は、現在の盆踊りなどで知られる河内音頭の原型と言われています。
南北朝時代の四條畷の戦い(1348年,正平3年)で、 楠木正行軍の軍師が交野村に落ち延び、戦死将兵を手厚く弔って念仏踊りをしたことが後に踊り継がれて盆踊りとなり、交野節となったとも言われています。
交野節は、北河内全域に広まるにつれ、節・囃はやし・太鼓・踊りの振り等に変化が生じますが、「七七七 五七五」の定型句と「ヨホホイホイ」の掛け声は共通しています。
明治時代になると、句の定型や節付けを自由に変化させて歌う歌亀節が創作され、後に初音節、鉄砲節が生まれました。
また、枚方市尊延寺地区に伝わる交野節は最古の節であるとされています。交野市内では、私市地区や星田地区で交野節が受け継がれています。
交野節の音源
交野市星田を拠点に活躍した音頭取りの方による歌を、民謡調査の一環で収録したものです。
外題の「葛の葉子別之段」は、現在の大阪府和泉市信太を舞台にした狐の伝説を歌ったもので、歌舞伎や浄瑠璃の外題「信太妻」としても知られます。