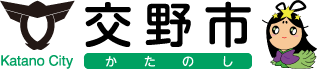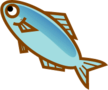公開日 2020年06月29日
「幼児食」とは、1歳6か月頃から5歳ごろまでの食事のことで、離乳食を卒業してからおとなの食事に近づけていく準備期間です。
幼児食は、大人になってからの食習慣の基礎となり、体や心の成長にとても大切です。偏食や遊び食べ、ムラ食いなど悩みごとが多い時期でもありますが、まだまだ食の経験が少ない年齢なので、あまり気にしすぎずにいろいろな食品や料理を取り入れていくようにしましょう。
家族みんなで食卓を囲み、楽しみながら、よい食習慣が身につくように心がけていきましょう。
目次
◇バランスよく食べましょう
◇食べやすく工夫しましょう
◇旬の味を取り入れて家庭の味を大切に
◇早寝早起き朝ごはん
◇親子で食を楽しみましょう
◆幼児期によくある食事の悩み(別ウィンドウ)
◆幼児食レシピ(別ウィンドウ)
◆幼児のおやつ(別ウインドウ)
バランスよく食べましょう
幼児期は成長が著しく、いろいろな栄養素が必要です。食品を上手に組み合わせて、バランスのよい食事を心がけましょう。また、この時期は味覚が発達する時期です。なるべく薄味となるように気をつけて、いろいろな食材を使って素材そのものの味を楽しませてあげましょう。
食事の量は大人の1/2~1/3量が目安ですが、個人差が大きいものです。少量ずつでもよいので、偏らないで食べられることが大切です。
◆3色そろえて、バランスよく
3色とは黄・赤・緑の3色です。黄色は〈米・パン・麺〉などの主食となるもの、赤色は〈肉・魚・卵・大豆製品〉などのメインのおかずになるもの、緑色は〈野菜やきのこ・海藻類〉で、それぞれの働きが異なります。
献立を考えるときには、「黄・赤・緑が全部そろっているかな?」とか、「昼ごはんはパン(黄色)だけだったから、夜はお肉やお魚(赤色)と野菜(緑色)をしっかり食べよう!」など少し振り返る時間を持つことで、何色が足りないのか、何色を摂り過ぎたのかが自然と見えてきます。
また、子どもにも「黄色は体が元気になるパワー」「赤色は体が大きくなるパワー」「緑色は病気に負けないパワー」がもらえるよと、お話ししてあげるとわかりやすいです。
|
き (主食) |
炭水化物を主とした料理 |
ごはん・パン・めん類など
|
|
あか (主菜) |
たんぱく質を主とした料理 |
肉・魚・卵・大豆製品など
|
|
みどり (副菜) |
ビタミン、ミネラル、食物繊維を主とした料理 |
野菜・果物・海藻・きのこなど
|
食べやすく工夫しましょう
「離乳食ではパクパク食べていたのに、急に食べなくなった」という相談も多く聞かれます。その理由には好き嫌いが出てきたというよりも「食べにくい」から食べないことがよくあります。
幼児は大人に比べて消化吸収能力やかむ力もまだまだ未熟だからです。乳歯が生えそろうのは3歳頃。 乳歯の生え方、口の動き、飲み込む様子をよく見ながら、食材の大きさやかたさを 工夫することが大切です。
また、味付けは素材の味を生かしながら控えめにつけるなどして、ゆっくり すすめていくのがおすすめです。
また、大人の食事もうす味を心がけましょう。
|
野菜類 |
★葉もの野菜など薄いものは、ペラペラしていて奥歯が生えそろわないうちはうまく噛めません。細かくして他の料理(ハンバーグ・ピラフ・ミートソースなど)に混ぜたり、スープや汁物に入れてやわらかくしましょう。 ★野菜のもつ苦味や酸味、辛み、青臭いような味は、大人はおいしく感じても子どもは苦手とする子が多いものです。 ・例えば、ピーマンの青臭さや苦味は色が悪くなるくらい下ゆでしてから炒め、さらに蒸し煮に。初めはごく少量を使い、少しずつ慣れるようにしていきましょう。 ・だしの味やうま味のある食品(肉・油揚げなど)と組み合わせてうま味を効かせましょう。また、マヨネーズ・ピーナッツバター・炒りごまなどで和えると苦味が和らぎます。 |
|
魚 類
|
★魚が苦手な原因は、生臭いことや、骨があって食べにくいことです。 なるべく新鮮な魚を使うこと。カレーやケチャップ、チーズなど好きな味をつけることや、小骨はていねいに取り除いてあげましょう。 ★蒸し焼きにすると魚の身もやわらかくなります。ふたをして蒸し焼きにすることで、パ サパサしがちな魚もやわらかく仕上がります。 ★新鮮なもの、身がやわらかいものなら食べやすく、子ども用にも取り分けしやすいです。煮魚は味が濃くなりやすいので、薄味を心がけましょう。 |
|
肉 類
|
★お肉が苦手な原因の多くは、かたいスジが口に残って食べにくいことです。特に、うす切り肉は、弾力がなく加熱するとパサパサするので、うまく噛み切ることができません。繊維を断つように切る、厚みのあるものと組み合わせる、下味や粉をつけるなど工夫をしてみましょう。 特に、1歳代は、基本的にはミンチ肉を使うとよいでしょう。 ★肉は加熱すると焼き縮みしてかたくなりがちです。片栗粉をまぶしてほぐしてから炒めると、ふんわりとソフトな食感に仕上がります。 ★ハンバーグなども豆腐や野菜を入れてふんわりと仕上げましょう。 |
★炒め煮(炒めてから、少量の水やだし汁を加えて煮る)や蒸し煮(水分を足してからふたをして蒸す)は、 固さを調節しやすく、子どもも食べやすくなる調理法です。 また、少量の調味料でも味が全体にいきわたり、うす味でも美味しく仕上がります。
旬の味を取り入れて家庭の味を大切に
◆旬の食べものは生命力がいっぱい
旬は自然の摂理にしたがってのびのび育った作物が市場に出回る頃で、味が美味しく、栄養素もたくさん含まれています。例えば冬のほうれん草のビタミンCは、夏の時期の3倍も含まれているのです。 今では、栽培や輸送の技術が進み、いつでも美味しく作れるので、1年中あらゆる食材が店頭に並んでいますが、旬のものは量もたくさん出回るため、低価で購入できるので家計にも優しいです。 味覚が形成される幼児期に、栄養価が高い旬の食材をできるだけ選び味わっていきましょう。
◆旬を味わう味覚を育てよう
旬の食材を中心に、季節感のある献立を取り入れましょう。 例えば、春には筍ごはん、夏にはトマトやキュウリを冷やして丸かじり、秋にはサンマの塩焼き、冬には ほうれん草、白菜などをたっぷり使った鍋ものなど、その季節ならではの食材のもつ味を味わいましょう。 うす味で調理することで素材そのものの味が感じられ、味覚も磨かれていきます。
◆収穫体験
いも掘り、いちごやみかん狩りなどに出かけることで、旬の時期ならではの楽しい体験ができます。
早寝早起き朝ご飯
私たちの身体には「体内時計」が備わっていて1日の生活リズムを正確に刻んでいます。 しかし、体内時計と地球の自転が約15分ずれているため、体内時計をリセットしないとどんどんずれが広がり、体調不良の原因にもなります。そこで体内時計をリセットするためには、朝日を浴びることと、朝食をとることが大切です!
♪朝ごはんのはたらき♪
🌞体温をあげる
睡眠中は、私たちの体温は低くなっています。朝起きた直後はまだ体温が低い状態です。 朝食を食べることでからだ全体が目を覚まし、体温は徐々に上昇し始めて元気に動けます。
🌞脳が目覚める
朝ごはんを食べて脳にブドウ糖が送られると、脳は元気に活動し始め、やる気や運動能力、集中力が アップします。
🌞腸の働きがよくなる
食べ物が入ると胃から脳へ信号が送られ、排便を促す「胃・大腸反射」が起こります。特に朝はこの反射が強く起こるため、体の中の流れがスムーズに!
🌞肥満を防止する
朝食を食べることで体内時計のリズムが整うと、脂肪や糖を燃焼させる細胞が増えたり、筋肉の合成を手伝うたんぱく質が活性化して代謝効率がアップし、肥満防止にもなります。
♪朝食をそろえるための一工夫 ♪
*前夜に少しでも準備しておくと、安心です!
| ごはん | ・ラップでおにぎり!具は、鮭・しらす・ハム・ウインナー・ふりかけ・ごまなど ・おじややリゾット!前日に残った汁物に、ごはんを入れて卵でとじる |
| パン | ・チーズトースト (玉ねぎ、ベーコン、スライスチーズをのせて、ピザ風に) ・サンドイッチ (ハムやきゅうり、卵をはさんで) ・ホットドッグ (バターロールにウインナーや卵をはさんで) |
| 野菜など | ・野菜などの具をたくさん入れたみそ汁やスープなどの汁物の作り置き ・温野菜サラダ(耐熱容器に、カボチャ、ニンジン、ブロッコリーなどの野菜とバターを入れてチン!) |
♪朝食をおいしく食べるための工夫♪
◆早寝早起きで生活リズムを整える
◆早めの夕食を心がける
◆夜の下準備で朝の調理時間を短縮する
親子で食を楽しみましょう
自分から食べようとする意欲をどんどん引き出し、何でも食べられるようになるには、まずは食事を楽しむことが一番です。叱られたり、大人がイライラしたりしていることが多いと、食卓がつまらない場になってしまいます。楽しいことやほめられる体験が多いほど、子どもはいろいろな食べ物にチャレンジする意欲がわいてくるものです。叱るよりも、発達に合わせながら楽しい食事の時間を増やしてあげましょう。
お手伝いや買い物などの体験、パパやママの言葉からも「食べること=楽しいこと」を発見させてあげましょう!!
また、子どもに合った調理の工夫は必要ですが、そのために特別に作るのではなく、大人のごはんをベースに食材の大きさやかたさを変える、薄めの味付けにするなど工夫をして、「取り分けられるメニュー」にすることで、親子で同じごはんが食べられます。
大人の食事を取り分けて作ることで手間も減り、同じものを食べられるので子どもにとっても嬉しいことです。
◯「おいしいね!」「楽しいね!」の言葉かけ ◯食べ物についてのお話
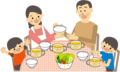



◯収穫体験 ◯一緒にお買い物


◯絵本の読み聞かせ ◯出来ることのお手伝い